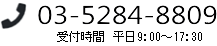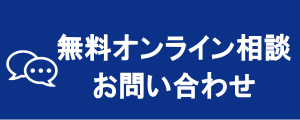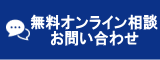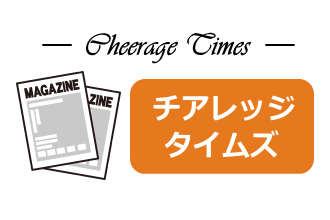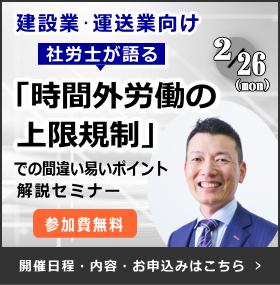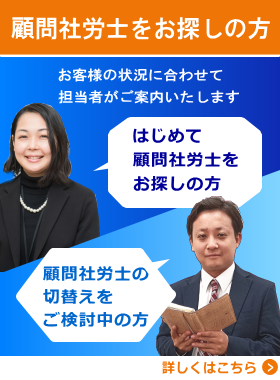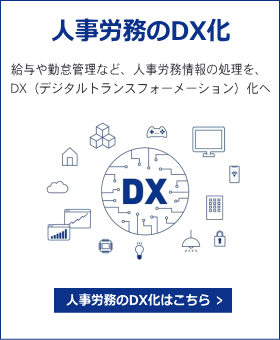~代表・三輪康信からのメッセージ~
「人間の心の成長にとって最高の栄養は本」―建築家・安藤忠雄さんの言葉―
社内木鶏会感想文 & チアレッジタイムズ委員会より

「人間の心の成長にとって最高の栄養は本」―建築家・安藤忠雄さんの言葉―
「致知」(2025 年6 月号)の特集「読書立国」に建築家の安藤忠雄さんとノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授のお二人の対談記事がありました。
山中教授は読書の意義として次の二つを挙げられています。
1. 大作を読むことは著者との格闘。時間もエネルギーもかかる。でも、その分だけ集中力、忍耐力、持続力、探求心といった長い人生を生き抜く基礎体力が身につく。
2. 自分だけでは経験できない他の人や過去の人の生き方や価値観を学べる。自分もかくありたいという目標を与えてくれる。それが向学心や向上心に繋がっていく。
「なんだ、本か・・・」 と思ったけれど
12 歳の誕生日に父から贈られたプレゼントは『三国志』(吉川英治著)の8 巻セットでした。大きな箱をワクワクしながら開けたら、米粒のような小さな字がびっしり並ぶ本。「なんだ、これ!」と驚きました。父は「活字の本くらい読め」と私に渡してくれたのですが、正直、「拷問か」と思ったものです。
それでも「親からのプレゼントだしなぁ」と四苦八苦しながらも読み進めていくうちに、次第に物語の世界に引き込まれ、気づけば夢中になっていました。読み終えた時の達成感と、清々しさは、今でも鮮明に覚えています。「大作を読むことは著者との格闘。人生を生き抜く基礎体力が身につく」―山中教授のこの言葉は、あの時の私にぴったりです。
改めて12 歳の私に本を贈ってくれた父にとても感謝しています。
180 度変わった環境で悩んだ時に…
『三国志』をきっかけに読書好きに…ということもなく、それからもしばらく活字離れの日々を送っていました。私は元々が体育会系、新卒で入った会社も、怒号や罵声が飛び交い、パワハラも当たり前、「力で抑え込む」ことが正義のようにまかり通る世界だったんです。
そんな私が別の職場に移った時、それまでのやり方は一切通用しなくなり、途方に暮れました。なのに「悪いのは周りだ」と思い込む気持ちは抜けず、どんどん孤立していきます。数年間、八方塞がりの中で、もがき続けた末に、書店で手に取った一冊が『マクドナルドの人材育成』でした。27 歳の時です。
そこに書かれていたのは「まずは自分が変わらなければダメだ。とにかく汗をかけ」という言葉。馬鹿の一つ覚えのように、階段を丁寧に濡れ雑巾で毎日、拭き始めました。わざと汗をかいたりして。最初は、みんなしらけた表情で通り過ぎていきました。
でも、続けていると、声をかけてくれる人が出てきます。挨拶してくれる人も少しずつ増えてきて、少しずつマネジメントの「マ」の字ぐらいができるようになっていったように思います。読書によって気づきを得て、内省し、行動を変えられた、今、思い返しても、この体験は私にとって大きなターニングポイントでした。
「大作を読むことは著者との格闘」
それからも必要に迫られては、いろいろな本を自分にノルマを課すように読んでいます。累計で1000 冊以上になっているのではないでしょうか。世の中には「本が好き!活字が好き!」という人もいて、つくづくすごいな!と思いますが、私は、必要に迫られた本を「よし!今日はこれだ!」と手にとり、集中するために家を出て、喫茶店などに行って読んでいます。平日は朝6 時に出社して、30 分間、読書をすると決めています。
「なかなかうまくいかない。どうしたらいいんだ」とあがき、本を手にとる、心が揺らぎ、自分の心が整っていないことを感じて、また本を読みだす…今もなおその繰り返しです。
どれだけ集中して、その本にとりかかれるか、学び、吸収できるか。私にとって読書とは嗜好品ではなく、まさに「挌闘」です。分厚い本を「まだこんなに残っているのか」と溜息まじりにページをめくっている時もありますが。
「読書→気づき(内省)→実践」、この繰り返しこそが人を成長させてくれる
壁にぶつかった時、著者がどんなことを感じ、どう行動や考え方を変えて乗り越えたのか―そんな体験談に触れるたびに、自分の中に新しい気づきが生まれます。「読書→気づき(内省)→実践」、この繰り返しこそが人を成長させてくれるのではないでしょうか。
人生では、心ない言葉を投げつけられたり、理不尽な出来事に遭遇したり、心が乱れることが何度もあります。そうした日々が続けば、知らないうちに心が荒みます。
そうなれば、心の余裕を失い、他人に優しくすることもできません。怒りや恐れで、心がいっぱいになってしまうから。けれど、器の大きい人は違います。自己概念を高く持っている人は、心がかき乱されるような出来事に直面しても揺らぎません。
また、立場や環境が違えば、見えている世界はまったく異なりますが、そのギャップを埋め合い、認め合う、利己的になりがちな自分の心を、少しずつでも利他的に整えていく―それも「器を大きくする」ことかと思います。
私は読書が好きでも得意なわけでもありません。でも「心の栄養」になっているし、荒れがちな心を整えて、「より良く生きるための原理原則」に気づき、戻してくれる力を感じています。読書を通じて、違う価値観や考え方に触れ、受容力を高め、器を大きくしていこう!そう思いながら、「よし!今日はこれを読むぞ」と本を手に取っています。
【社内木鶏会 感想文】
| *人間学を学べる月刊誌「致知」をテキストに「社内木鶏会」を毎月、開催しています。全員が指定された記事の感想文を発表し、その中で選ばれた感想文です。
<対談 人を幸せにする経営のあり方> 「かんてんぱぱシリーズ」でおなじみの長野県の伊那食品工業は、年輪経営に軸足を置いた独自の経営で知られる。貧困や病など多くの逆境に見舞われながらも、試練を逞しく乗り越えて有名企業に育て上げた最高顧問塚越寛氏。その人生や経営に対する思いを、長年の知己で氏を敬愛する、俳優で仏像彫刻家の滝田栄氏にお聞きいただいた。 |
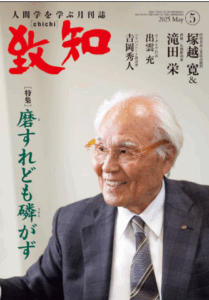 |
<今月の選出感想文>
伊那食品工業は、揺るぎない経営理念のもと、社員をはじめ会社に関わるすべての人々の幸せを目的とし、会社の存在意義をそのための「場」と捉えている。創立から半世紀以上の歴史を持ち、樹木が一年に一本、年輪を刻みながら、天候に左右されず着実に成長する姿に喩え「年輪経営」を経営の軸としている。そして、最高顧問塚越氏は、伝教大師最澄が説いた「忘己利他」の教えに、会社の理想の姿を重ねている。
「忘己利他」とは、自分を忘れて他社のために尽くすことこそが、慈悲の極みであるという教えだ。自分を少し抑え、人が喜ぶことを行うことで、幸せが生まれる。会社も同じく、社員の幸せを最優先する経営を続けることで、巡り巡って会社の利益へと繋がり、年輪のように発展していく。
私は、この「忘己利他」を否応なく経験したことがある。それは、新生児の育児期間だ。赤ちゃんは産声を上げた瞬間から、2~3時間おきに泣く。空腹、オムツ交換、暑さ寒さ、抱っこを求めて泣き続ける。昼夜の区別なく、己を忘れ対応せざるを得ない。まるで修行僧のようだ。
しかし、その一方で、赤ちゃんは生理的な微笑を見せたり、手の平に指を置くと反射的に握り返してくれたりする。その姿はとても愛らしい。そして、言葉を発するようになり、寝返り、つかまり立ち、一人歩きへと成長する過程は、数多くの感動をくれ自分の幸せへと還元されていく。
会社経営について考察するのは恐れ多いが、自分を「自らの人生の経営者」として捉えれば、「年輪経営」は非常に参考になる。私の「細く長く」という人生設計とも一致している。年輪は樹木ごとに異なり、どれひとつとして同じものはない。それは人の人生と同じだ。この「年輪経営」を実践するため「忘己利他」の教えを参考にしたい。他者の幸せを追求することで、それが巡り巡って自分の幸せへと繋がるのだ。
では、幸せの源泉とは何か。それは「感動」にほかならない。そして、感動を生み出すにはどうすればよいか。それは、相手の事前期待値を超えること。期待値を超えるためには、日々の作業を単なるルーティンとして捉えない。小さな工夫や、一歩先を考えることで、誰かの期待を超える瞬間をつくり出せる。その積み重ねが、人の心を動かし、幸せへと繋がっていく。大切なのは、実践すること!その「場」はチアレッジが提供してくれている。
〔労務チーム:和泉 美絵〕
【知識のアップデート ~勉強会~】
 |
チアレッジでは毎月、木鶏会と合わせて、全員出社日に「勉強会」を開催しています。勉強会では、労務知識はもちろん、DX に強い社労士事務所として、皆でシステムの知識を深めます。新しい機能が追加された、便利な機能を発見した等、勉強会を通して情報共有をしながら、日々最新の情報にアップデートし、お客様へ有益なサービスをご提供できるよう、成長し続けます! |