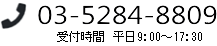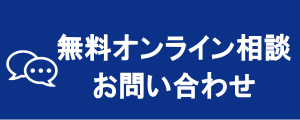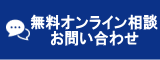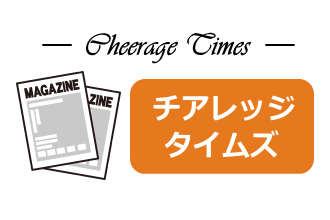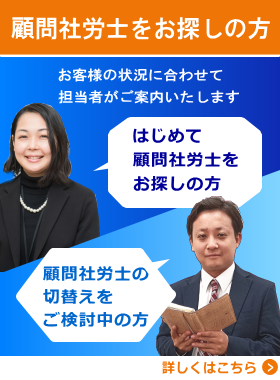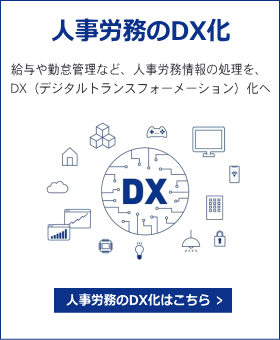~代表・三輪康信からのメッセージ~
「賃上げ」は今や「企業の生き残り戦略」、それをしないと生き残れない
社内木鶏会感想文 & チアレッジタイムズ委員会より

人手不足による倒産が過去最多に。これからさらに増えていく
「『賃上げ』できなければ退場 人手不足で淘汰加速」、日経ビジネス誌(2025.2.14 号)の記事のタイトルです。「人不足時代」です。年々、人が集まりにくくなっていますし、人の奪い合いになっています。
2023 年11 月、飛騨地域で11 店のコープを展開してきた日田農協農業共同組合は「1 店舗を残し、他店舗は一斉閉店」と発表しました。原因は「競合するスーパーやドラッグストアの進出」ですが、致命的な追い打ちをかけたのが「人手不足」です。
コープの時給が最低賃金の近辺にある一方、インバウンドで潤う宿泊施設や飲食店は破格の時給を示して人をかき集め、「とても太刀打ちできなかった」。つまり、賃上げができないがための人手不足による倒産です。同業他社との競争だけではなく、そういう時代です。
少子高齢化がどんどん進み、社会保障の財源確保のため、税金も上げていこうというトレンドにあり、物価もどんどん上がっています。従業員を大事にしよう、働いている人たちの生活水準を同等以上に維持していこうとするならば、物価水準、社会保険料の増加を上回るスピードでの賃上げを経営者は考えていかなければなりません。
この30 年間、賃金が上がらなかった日本で、今、その状況が音を立てて崩れ、動き始めているのに、それを感じていない経営者もまだ多いのではないでしょうか。人手不足はこれからますます深刻化します。賃上げできない会社は人が来ず、潰れていく、その淘汰が加速していきます。今や「人材確保」は企業の生き残り戦略の最優先課題です。
「必要なのは、経営者の覚悟だ」
「『中小中堅企業だからとか価格転嫁できないから賃上げは無理』は言い訳。必要なのは、経営者の覚悟だ」(坂口捺染の坂口輝光代表)、私は、この言葉に強い衝撃を受けました。「賃上げする」と決めて、言葉にすれば、どうにかこうにかやる方法を探すもの。「覚悟」だ。「うちの業界は…」「うちの会社の規模では…」は言い訳だと。
イオンは2023、24 年と二度にわたってパートさんの時給を7%引き上げました。「小売業の巨人だから」と思われるかもしれませんが、25 年1月発表の決算は2 年ぶりの赤字、それでも「今後も手を緩めず、7%の賃上げを実施する方針」と言っています。巨大企業がその方針で動くのであれば、当然、中小企業にも影響が出てきます。
石破茂新政権は「最低賃金を全国加重平均で1,500 円に引き上げる」という政府目標の達成時期を、従来の「2030 年代半ば」から「2020 年代」へと前倒しする方針を打ち出しました。2029 年までの5 年で455 円あげなければなりません。年間100 円弱です。
国が用意している雇用関係の助成金は「生産性を上げるための設備投資」「従業員のリスキリング研修」といったところにどんどんお金をつけています。ここに取り組む会社は生産性も上がるから、賃金も上がり、生き残っていきますが、「それができないのであれば、淘汰されていってください」というメッセージではないでしょうか。
ワーク・ライフ・バランスも大事だけれど
最近、とってもバイタリティに溢れ、優秀な若者に会いました。彼はたとえ週末であっても連絡すると、すぐに返信をくれます。「仕事、楽しいですか?」と聞くと「楽しいです!」と笑顔で返してくれ、こんなこともさらりと言います。入社4 年目だそうですが「12 年目だと周りの皆さんには言ってます。なぜなら人の3 倍働いてるからです!」。こういう人に会うと、こちらまで元氣になります!
「ワーク・ライフ・バランス」が言われ、それも大事です。けれどもイキイキと働く彼を見ていると、こんな元氣な人が世の中に増えたらいいなとワクワクします。大切なのは、自分の選択でやっているかどうかだと思います。
頑張ったら頑張った分だけ報われる制度づくりをしていきたい
一概に「賃上げする」といっても、成果型に振り切った賃金制度型、ストックオプションをつける、福利厚生を厚くする、「終身雇用、年功序列」をうたう会社もあります。
私は自分の会社では成果型、「頑張ったら頑張っただけ報われる」制度づくりをしていきたいと思っています。「チームワークが乱れるのでは?」「個人主義に走るのでは?」という話も必ず出てきますが、そうならない仕組みも整えながら、やってみなければ分からないこともあるし、まずはやってみようと。
それぞれの会社の風土、働く人たちはどんな人が多いか、そうしたことによって様々な選択肢が出てきます。とはいえ、とにかく「賃金は上げていかなければならない」、そうしないと生き残れない時代です。
人手不足による倒産はこれからますます増えていきます。「賃上げの大合唱はやまず、対応できない企業の末路は厳しい。物価上昇を上回る生産性を確保できるかが、生き残りのカギになる」と記事にもありました。
企業の独自性を出しながら、どう工夫して人事制度を構築していくか、要は「頑張ったら頑張った分報われる制度」をいかにつくっていくか。これは私が今後の職業人生をかけて研究していくテーマだと思っています。
【社内木鶏会 感想文】
| *人間学を学べる月刊誌「致知」をテキストに「社内木鶏会」を毎月、開催しています。全員が指定された記事の感想文を発表し、その中で選ばれた感想文です。
<鼎談 2050年 日本を富国有徳の国にするために> かつて地中海全域を支配し繁栄を築いた古代ローマ帝国は、ローマ人がローマ人たらしめているものを失ったから滅びたという。では、日本を日本たらしめているものは何だろうか。その一つは「勤勉・修養の精神」である。 |
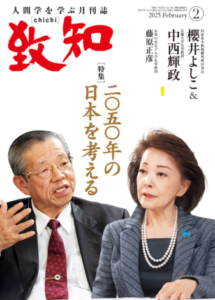 |
<今月の選出感想文>
日本を特徴づける要素の一つとして挙げられる「勤勉・修養の精神」。日本人はよく働き者や努力家だと言われているが、現在の日本人にこの精神はどれほど浸透しているのだろうか。若い世代を見ていると、楽しそうにイキイキと生活している一方で、先生を尊敬する割合が世界的にみても
圧倒的に低いことや、AO 入試等により勉強へのウェイトが減少しているのではないかと感じることもある。勤勉・修養の精神が希薄になっているのかもしれない。
自由や個を尊重する教育方針には個人的には賛同だが、これが「日本らしくない」現状の一因であるとも考えられる。かつての協調性やチームワークといった日本人らしさが薄れ、個性や独自性が重視されるようになった結果、謙虚さや異質なものを受け入れる力が弱まっているのかもしれな
い。私自身も、集団行動よりも個人で黙々と作業しがちであるし、受け入れる力は弱いと感じるので、日本人らしくない一員なのだろう。特に社会人になってからその傾向が顕著になっている自覚があるため、周囲との協力やチームプレーを意識して行動していこうと改めて思う。
同じ「楽」という字でも、「ラク」と「楽しむ」では意味が異なる。ラクをしようとすれば、後でそのツケが自分に返ってくることは明らかだ。しかし、楽しんでいると自然とラクになるものだという。仕事も同様で、楽しむことが前提にあるからこそラクができるのだと。仕事を楽しむとい
う概念が希薄だった私にとっては新鮮で難しい発想だが、自分も周りもラクになれるように、たくさんの楽しみを見出していきたい。
〔管理部:野田 陽子〕
【ランチ会でパワーチャージ 】
 |
チアレッジでは、毎月1 回全員出社日があり、その日のランチは全員で揃って頂きます。普段、リモートワークや外出などで顔を合わせることが少ない社員とも、ここぞとばかりに近況報告をし合える貴重な場です。 休日の過ごし方や趣味の話、最近のトピックスなど、様々な話題で盛り上がります。次は誰と何を話そうかと、毎月楽しみなランチ会です! |