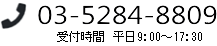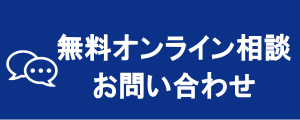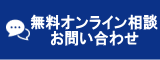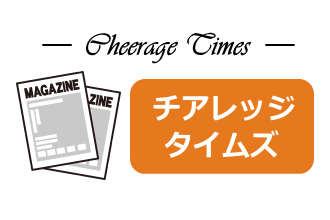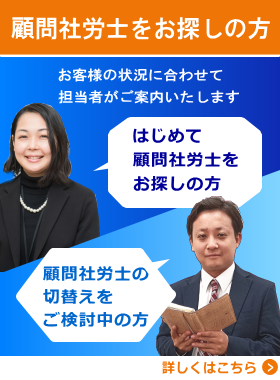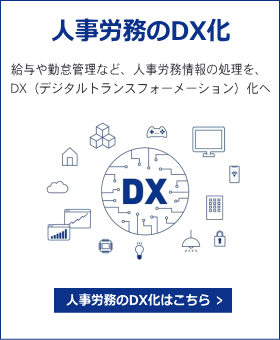~代表・三輪康信からのメッセージ~
「掃除の神様」、鍵山秀三郎さんの実践と哲学
社内木鶏会感想文 & チアレッジタイムズ委員会より

「掃除の神様」、鍵山秀三郎さんの実践と哲学
去る1 月2 日、イエローハット創業者の鍵山秀三郎さんが91 歳で逝去されました。一代で国内有数の自動車用品チェーンへと育て上げただけでなく、トイレ掃除を社会運動にまで高められ、「掃除の神様」としても知られています。私はお会いしたことがないのですが、鍵山さんが遺されたエッセンスが今なお、いろいろなところから伝わってくるんです。
トイレ掃除で社風が変わった
有名な話ですが、鍵山さんがカー用品販売の商売を始めた時、業界は非常に荒んでいて、職場でも社員の言葉遣いも悪いし、ゴミ箱を蹴とばす社員もいて、注意をしても一向に直りません。
そこで鍵山さんがしたのは、相手を批判することでもなければ、罰することでもなく、相手を思い通りに動かそうとすることでもありませんでした。朝一番に出勤をし、たった一人で、トイレ掃除を10 年し続けたのです。床に這いつくばってトイレ掃除をする鍵山さんの手をまたいで通っていく社員もいたそうです。その様子を想像するだけで涙がでます。
でも、やっぱりそんな姿に心を打たれて「私も何か役に立ちたい」と思う人が出てくるんですね。一人、二人と増えていき、良い社風ができあがっていった。一人の人間の真心、信念に裏打ちされた行動、その継続が成し遂げたということです。
どうしてそこまで掃除をするのか
「21 世紀の日本を開くリーダーを育てたい」と松下政経塾を立ち上げた松下幸之助さんは塾生たちに「立派な指導者になるための第一歩は、身の回りの掃除をしっかりやることや」と説いています。「日本を美しくする会」の会長を務められていた田中義人さん(東海神栄電子工業会長)も「トイレ掃除をすることによって社風が変わった」と語られています。「掃除は人の心をポジティブに変え、場のエネルギーを高め、組織を積極的にしていくようです」と。
掃除をすれば、きれいになります。人間は「環境の生き物」です。目に触れるものが汚いか、ピカピカな、きれいな状態かどうかで心の状態が違いますし、掃除は成果がすぐに見えます。「自分できれいにした!」となれば、自己肯定感が高まり、もっと気分も良くなります。
イエローハット社とは真逆に、同じ車関係の会社でも、少し前に世間を違う意味で驚かせた会社がありました。故意に車を傷つけて修理代金を水増ししたり、はては店の前の街路樹を除草剤を撒いて枯らしたり…。会社ぐるみで売上げをつくるためにそこまでできるのか…と驚愕しました。
これほどまでの違いは何から来るのか。それはやはり経営者の心、思考ではないでしょうか。経営者であればこそ、自分を正すことの必要性を改めて感じます。
掃除で磨かれるのは・・・
人間は自分勝手な生き物です。自分が一番可愛いし、自分中心で物事を考えてしまいます。でも人間としての正しさは「他者中心で物事を考える」ことにあり、そうすることによって人生が拓けたりもするのに、どうしてもエゴが出てきてしまうものです。
また、経営者とは、自らの手を動かすのではなく、人の手を介してマネジメントをする人です。自分で何もかもやっていたら、組織がまわりませんから、そのことに長けてなければなりません。ですが、そうなればなるほど「自分中心」に考えがちになってしまいます。
かの車の販売会社の社長が這いつくばってトイレ掃除をしている姿なんて想像もできません。崇められることに慣れ、流れに任せていると、奢りや慢心が出てくるもの。成功している経営者の方々は、このことをしっかりと自覚され、日々、「自身の心を整えること」を実践している人が多いように感じます。
「日本を美しくする会」のホームページに「掃除の〝力〟」として〔①謙虚な人になれる ②気づく人になれる ③感動の心を育む ④感謝の心が芽生える ⑤心を磨く〕とありました。私も朝、起きたらすぐに自宅のトイレ掃除をすることを日課にしていますが、「掃除の〝力〟」を実感します。
「トイレ掃除」が象徴するもの
「掃除が大事」と分かっていても、日々の業務で手一杯になって余裕がなくなったり、不測の事態も起こりますから、そこに割く時間や優先順位はどうしても、下がってしまうものです。
ですが、鍵山さんは、何十年間と、常に「掃除」の優先順位を最上に置き続ける意思の力を持ち続けられました。「優先順位を下げよう」とする事象はたくさん出てきたはずです。内からも外からも。でもやり通された。素晴らしいなと思います。社員の心を変えただけでなく、巡り巡って私にも届いてきたように、社会に大きな影響を与えられた鍵山さんの偉大さに感嘆します。
鍵山さんは、自身の行動や思想に感銘を受けた人々から届く便りを、一通一通読み、返事を書き続けられました。その多くが感謝や励ましの気持ちに満ち、中には、200 通以上もやりとりを重ねた人もいたそうです。その総数は8 万5 千通にも上り、「脳梗塞で手が不自由にならなければ、10 万枚は書けたのに…と悔しがっていた」という逸話も残っています。
秀三郎さんの息子さんが対談で「親父はとにかく全て尊敬に値する存在」と語られていました。まさに「陰徳の人」、トイレ掃除をする姿は、その象徴のようにも思えました。
合 掌
【社内木鶏会 感想文】
| *人間学を学べる月刊誌「致知」をテキストに「社内木鶏会」を毎月、開催しています。全員が指定された記事の感想文を発表し、その中で選ばれた感想文です。
<対談 勝運を掴む> サッカーと野球。ともに日本代表監督として世界の大舞台で戦った岡田武史氏と小久保裕紀氏。得難い体験を糧にいま、それぞれFC 今治、福岡ソフトバンクホークスで目覚ましい実績を上げている二人は、いかにして己の運命と組織の可能性を切り拓いてきたのだろうか。名将が語り合うチームづくり、そして勝運の掴み方とは。 |
 |
<今月の選出感想文>
今治.夢スポーツ会長の岡田氏と、福岡ソフトバンクホークス監督の小久保氏の対談は、勝運を掴んだお二人の経験を通して、その過程にある大切なプロセスを学べると思い、今回選びました。
岡田メソッドとは、要約すれば「自立型人財の育成法」です。サッカーは攻守の入れ替わりが激しいスポーツであり、私自身も中学・高校時代に、同じく攻守が目まぐるしく入れ替わるバスケットボール部で活動していた経験があるため、その点は非常に共感できました。
こうした競技では、監督の采配がリアルタイムで届きにくく、選手一人ひとりがその場で自ら考え、判断して動くことが求められます。そのため、「自立して考える力」は極めて重要な要素であると改めて感じました。岡田メソッドは、ネット上でも「人的資本経営を支える人財育成の本質に迫っている」と評価されており、企業組織の成長にも大いに役立つものだと私は考えます。今後、より深く学んでみたいと思いました。
対談の中ではスペインサッカーについても触れられており、そこでは「まず原則を十分に学び、その後に自由がある」と書かれていました。この言葉を読んで、私は前職でスーパー銭湯の新店舗立ち上げに関わった際の出来事を思い出しました。その時、配属された後輩社員に「規律無くして、自由無し」という言葉を発して、伝えたことがあります。彼は目を丸くして、その言葉を受け止め、新店舗の理念やルール、マニュアルの重要性をしっかり理解してくれました。あの時のことが思い出され、改めて「原則」や「基礎的な知識・ルール」の大切さを実感しました。
また、岡田氏は「強いチームに共通する要素」として“主体性”と、もう一つ“多様性を受け入れること”を挙げています。私もこの点に強く共感します。人はそれぞれ異なるということを認め合い、共通の目的のために落としどころを探っていくことが大切です。そうでなければ組織としては機能しません。
まったくその通りだと思います。AI が急速に広がっていく今の時代にあっても、結局のところ、人と人が共に生きていくことに変わりはありません。会社という組織も、人が集まってこそ成り立つものです。多様性を受け入れたうえで、社内のルールや方針を決めたり、必要に応じて見直したりすることで、私たちのチアレッジも、より良い組織へと成長していけるのではないかと感じました。
〔労務チーム:寺田 光太郎〕
【梅雨入り前にチェック!】
 |
そろそろ梅雨入りの足音が聞こえてくる時期ですね。気圧や気温の変化で体調もゆらぎやすく、雨の日の通勤がちょっぴり憂うつになることも。こんな時季は、心と体のリズムに合わせて、少し余裕のある過ごし方を意識したくなります。夏の予定をぼんやり考え始める今、有休の管理や調整もこの機会にさりげなく見直してみてはいかがでしょうか。 |