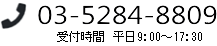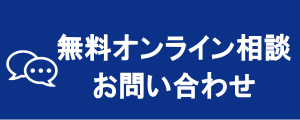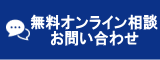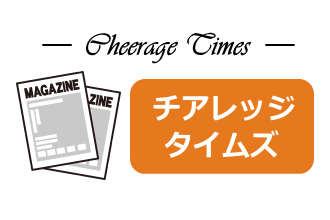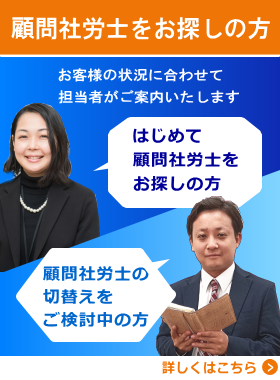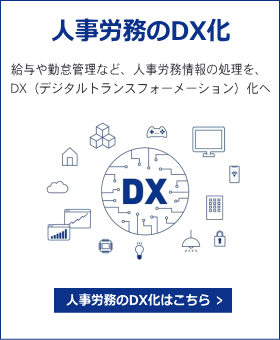~代表・三輪康信からのメッセージ~
「人と会社」が共に成長する人事評価制度
社内木鶏会感想文 & チアレッジタイムズ委員会より

「人と会社」が共に成長する人事評価制度
人財育成や公正な処遇のために多くの企業が人事評価制度を設けています。しかし、期初に「とりあえず目標を立てる」(注力比率10%程度)ものの、期中はほとんど放置され、半期末に慌てて取り組む。90%の力を注ぐのは、評価時期が目前に迫ったタイミング――。
日々のチェックや振り返りをしないまま、評価時期になって慌てても意味がありません。結果、公正な処遇からは遠ざかり、人財育成にも結びつかない――。「評価制度がうまく機能していない」と感じている企業は多いのではないでしょうか。
「目標によって自分を管理する」という考え方
ドラッカーが提唱した「MBO(Management By Objectives)」は、日本では一般的に「目標管理」と訳されていますが、元々は「自分で目標を立て、振り返り、目標によって自分自身をコントロールする」という自己管理の考え方を説いたものでした。
人事評価制度とは本来、この「自己管理」を支援するためのものなのに、うまく機能していない原因の一つに、「目標設定技術」の不足が挙げられます。
例えば、「半期の処理件数を現状の10 件から半年後には15 件に増やす」と具体的な目標設定をすれば「そのために何を、いつまでに、どうやるべきか」と考えるようになります。こうした思考力はスキルなので、やっていけば、引き上げていくことができます。
この力は、業務上の成果だけでなく、人間関係にも良い影響を与えます。例えば、相手から「できるだけ早くやります」と言われた時。こちらは「今週中にやってくれるかな?」と勝手に期待し、「まだできないのかな…」とやきもきする。でも、もしかすると相手は、あえて期限を曖昧にしたかっただけかもしれません。
「いつまでに、何をやるか」を意識して明言すること。そして目標をより具体的に考える習慣を持つことで、コミュニケーションが円滑になり、業務の効率化にも繋がっていきます。
曖昧な目標設定や思考からは曖昧な結果しか生まれない
弊社の人事評価制度は最初の目標設定に30%くらいの注力比率をかけています。上司と部下とでじっくり考えて目標を決め、そのための準備項目や期日をブレイクダウンするのですが、大事なのは「自分が立てた目標である」こと。モチベーションが違ってきます。
そして2 週間に1 回(月2 回)、自らの行動を振り返って記入したサポートシートを提出してもらい、上司がそこにコメントするのですが、記入時間は各々10 分程度。
「2 週間に1 回って多くないですか?」と言われます。でも、どうでしょうか?「緊急かつ重要」なことが日々、飛び込んできます。自分が立てた目標よりも優先度が低いことも含まれているのに、「緊急だから」とついそちらを優先してしまう…。その結果、自身の目標に向けた取り組みは後回しに――これでは、成果につながりません。
サポートシートはそのためのツールです。ここで設定する目標は3 つ。そして「スキル」「役割」で7 項目。「姿勢」「態度」で5 項目、計15 項目。これは各職種と等級ごとに決めていきます。項目を多くすると一見、立派なシートに見えますが、半期の間で人間、そんなに多くをこなせるものではありません。この設定はとても重要になってきます。
2 週間に1 回、本来の一番の目的を思い出す、確認する。だからこそ、しっかりした目標設定が大事だし、それがあるから思考もより明確になるのです。「曖昧な目標設定や思考からは曖昧な結果しか生まれない」、私の大好きな言葉です。
物心両面の豊かさを目指すために
私は常々、社内でも「物心共に豊かになりましょう」と言っています。そのためには自分の能力、スキル、人間力を高めていくことが欠かせません。職場の人間関係も大切です。憂鬱な環境なのか、「今日はあの人に会える!あの話がしたい!」とワクワクしながら向かう職場とでは、充足感は全く違います。
いい仕事をして相手に喜ばれれば、幸福を感じられます。これは、いわば『心の報酬』です。しかし、どんなにやり甲斐があり、職場がいい雰囲気であったとしても、給料が低いままでは生活は成り立たないし、続けていくことも難しくなるのではないでしょうか。
給料を上げるためには、まずは売上を伸ばすこと。そのための時間を効率化できれば、従業員に分配する余地が生まれます。「忙しいから…」と後回しにしていたことも「これが成長や報酬につながっている」と実感できれば、意欲的に向き合えるようになるはずです。
ロゴマークに込めた想い
弊社の社名「チアレッジ」は、「cheer up(応援する)」と「encourage(勇気づける)」を合体させた言葉です。コーチが選手に伴走しながらメガホンで「君ならできる!」「あとちょっとだ!」と声をかける様子をイメージし、メガホンの形を模したロゴを用いました。
私もマラソン大会に出場して実感したんですが、特に35 キロを過ぎた頃からの道端からの声援、とても励まされます。背中を押されます。「応援の力ってすごい!」と思いました。
人事評価制度の運用もこうした姿勢を反映させています。提出されたサポートシートに上司がフィードバックする際、大切にしているのは「承認と奨励」、目標が達成できていなくても「どうしたらできるようになるか」を一緒に考え、寄り添います。上司は期日を守る役割も担います。
「サポートシートがまだだけど、どうした?」と期日や進捗の確認をしながら、部下と一緒に目標に向かって進んでいく、つまり、上司は部下のコーチでありサポーターなのです。
こうした考え方をもとにした人事評価制度を導入された企業様からも「業績が上がった」「職場の雰囲気が良くなった」といった声を多くいただきました。評価制度とは「目標を通して人が育ち、会社も強くなる」、つまり人と会社が共に成長するためのものなのです。
【社内木鶏会 感想文】
| *人間学を学べる月刊誌「致知」をテキストに「社内木鶏会」を毎月、開催しています。全員が指定された記事の感想文を発表し、その中で選ばれた感想文です。
<対談 読書は国の未来を開く> 活字離れが進む中で、子供たちに本を読む楽しさや豊かさを知ってもらい、無限の創造力や好奇心を育んでほしい―。日本を代表する建築家・安藤忠雄氏のこの思いが結晶して生まれたのが「こども本の森」プロジェクトである。 |
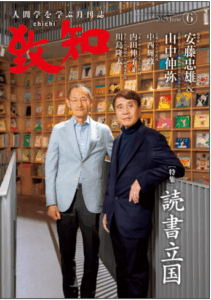 |
<今月の選出感想文>
「読書は国の未来を開く」という言葉に、最初は少し大げさにも感じましたが、記事を読み進めるうちに、その意味がじわじわと心に響いてきました。
本を読むことで、一人ひとりが考える力を養い、自分の言葉で語れるようになる。それが積み重なっていくことこそ、社会や国の未来を支える力になるのだと思います。読書の力は目に見えにくいけれどだからこそ大切にしたいと感じました。
私自身、小学生のころは本を読むのが好きで、物語の世界に没頭しながら、自由に空想を膨らませたり、未来を思い描くことが楽しかったのを覚えています。けれど今は、日々の忙しさの中で読書の時間がすっかり減ってしまいました。
スマートフォンや動画など、手軽に楽しめる娯楽が増え、情報は短くまとめられて提供される時代。すぐに結論を求める傾向は、一見効率的で理にかなっているように見えますが、一方で「自分で考える力」や「心の豊かさ」を削ってしまっているのではないかとも感じます。
最近の私は、ほとんど読書ができていませんが、それでも我が子には本が好きな子になってほしいと思っています。読書好きかどうかは、才能や性格の問題ではなく、「身近に本があるかどうか」「本と触れ合う時間が日常にあるかどうか」によるところが大きいと感じています。
だからこそ、自分自身がまず読書の時間を取り戻し、子どもと一緒に本に向き合う習慣を少しずつでもつくっていけたらと思いました。
「読書」は、誰かの意見に流されるのではなく、自分の頭で考え、自分の足で生きていく力の糧になる――。そんな思いを胸に、もう一度、本の世界に戻ってみたいと思いました。
〔DXチーム:林 景子〕
【チアレッジからの手紙 更新中!】
 |
弊社ホームページでは、毎月『チアレッジからの手紙』を掲載しています。 新しい仲間も増えましたので、新メンバーの内面を覗いてみてください!趣味の話や家族の話、日々感じたこと等、思ったことを書き連ねています。 個性豊かなお手紙、ぜひご覧ください! https://cheerage.co.jp/category/topics/daily/ |